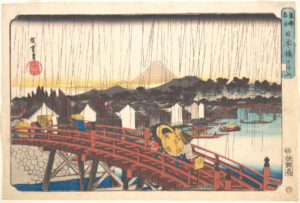STUDY
2025.4.30
最後の晩餐(レオナルド・ダ・ヴィンチ)を理解する3つのポイント【名画解説】
レオナルド・ダ・ヴィンチが残した『最後の晩餐』は、日本でもっとも有名な西洋絵画の1つでしょう。ルネッサンスを支えた万物の天才レオナルド・ダヴィンチは、芸術の世界においても革新的な存在でした。
 レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
最後の晩餐は、挑戦的な絵画技術の導入や、伝統にとらわれない人物の構図、当時の絵画表現において新しかった「遠近法」が特徴です。この記事では、イタリアの大学院で美術史を学ぶ筆者が『最後の晩餐』をわかりやすく解説します!
最後の晩餐の概要
 レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
最後の晩餐は、1495~1498年にかけてイタリア・ミラノのサンタ・マリア・デッラ・グラツィエ聖堂に隣接している修道院の食堂に描かれた作品です。『最後の晩餐』というテーマと「食堂」の場所に組み合わせは、「食べること」における関連性が意識されたのかもしれません。
レオナルド・ダ・ヴィンチは絵画作品の多くを未完で残したため、完成している『最後の晩餐』は非常に珍しく貴重です。レオナルド・ダ・ヴィンチが不安定な新しい絵画技術に挑戦したことや、食堂という場所の条件(湯気や湿気が多い)により損傷が大きく、何度も大規模な修復がほどこされてきました。
ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』特徴①:絵画技術
 レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』は、独自的な絵画技法で制作されたことで有名です。『最後の晩餐』のように壁に絵を描く際、西洋絵画では伝統的に「フレスコ画」と呼ばれる技法が用いられてきました。「フレスコ画」は湿気に弱い弱点があるものの、化学変化を利用するため色の耐久性が強い特徴があります。
レオナルド・ダ・ヴィンチは元来、このフレスコ技法を好んでいなかったと言われます。フレスコ画は石膏が乾く前に色を塗って色彩を定着させるため、瞬間的な作業が必要でした。継続的に思考しながら追加、修正を加えることを好んだレオナルド・ダ・ヴィンチにとって、フレスコの相容れない性質の技法だったのでしょう。
レオナルド・ダ・ヴィンチがフレスコの問題点(すぐに絵を完成させる必要がある点)を解決するために応用したのが、パネル画のテンペラ技法です。下地にはフレスコに用いられるのと同様に石膏を塗布し、石膏の上に下書きを加えてテンペラ技法で色付けをしました。
レオナルド・ダ・ヴィンチが挑戦したこの技法は、洗練された色彩と透明感を実現しただけでなく、細部への徹底的なこだわりを可能にしました。しかし一方で耐久性に欠ける問題点があり、作品が完成してすぐにひどく損傷してしまったそうです。
1566年に作品を見たヴァザーリ(イタリアの芸術家記録者)は「汚れしか見えない」と残したほど、作品は劣化してしまいました。劣化の原因は定着性の低いレオナルド・ダ・ヴィンチの新技法と食堂の湿度の高さと考えられます。
長年の修復作業をつうじて現在でもなんとか作品の輪郭は維持されていますが、それでも美術史上「もっとも問題の多い傑作」と呼ばれるほど課題が多いのが現実です。度重なる大修復により、使徒たちはほとんどレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたものとは言えないと評価する美術家もいるほどです。
ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』特徴②:人物構図
 レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
『最後の晩餐』は、みなさんご存じのように十二使徒のうちの1人がイエスを裏切ることを予告するシーンを描いています。裏切り者のユダは銀貨30枚の代わりにイエスの情報を売ったと言われます。
それまでの伝統的な『最後の晩餐』の構図では、イエスを含めたユダ以外の11人の使徒がテーブルの奥に、ユダがテーブルの手前に配置されることが一般的でした。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』では、全員がテーブルの向こう側におり、それぞれがドラマチックな反応を見せています。
両手を開いて無実を示す者、隣の者に話しかける者、思わず立ち上がる者…、一見バラバラな行動をとっているように見える使徒たちですが、実は全体的にイエスを中心とした構図になるように配置されています。
レオナルド・ダ・ヴィンチが作った全体的な構図は細部にまで注意が払われており、テーブル上の食器や備品なども構成要素です。これはもちろん背景とのバランスも重要で、イエスを中心にして全体が放射状に広がるような圧倒的な存在感を与える効果があります。
ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』特徴③:遠近法
 レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
レオナルド・ダ・ヴィンチ, 『最後の晩餐』, Public domain, via Wikimedia Commons
遠近法は、近くのものが大きく、遠くのものが小さく見える原理を利用して絵画に3次元的な印象を与えるテクニックです。ルネッサンスと遠近法の発見(再発見)の関係は深く、写実的な絵画構図にはなくてはならない考え方でした。
先述したイエスを中心軸とした構成は、遠近法とも関連があります。修復の際にイエスの頭あたりに釘を打ったあとが見つかったことから、レオナルド・ダ・ヴィンチはイエスの頭を遠近法の消失点に設定していたとわかりました。
背景の3つの窓から入る光と左右の壁の模様(おそらくタペストリー)により作られた遠近法は単純であるものの、使徒の体勢やテーブルの配置の効果で絵画全体がより深い印象を与えます。
全体がイエスから発生しているような、反対にイエスに向かって集約しているような、イエスの超自然的な孤立感はレオナルド・ダ・ヴィンチの緻密な計算によって作られたものでした。
レオナルド・ダ・ヴィンチの作品はさまざまな憶測や議論を呼ぶことが多く、それゆえ世界中の人に愛され続けてきました。作品鑑賞の際は、構図とテクニックに注目してくださいね。以上、レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』の解説でした!

画像ギャラリー
あわせて読みたい
このライターの書いた記事
-

STUDY
2025.09.30
イタリアの世界遺産の街7選!歴史と美術の面白さを在住者が解説

はな
-

STUDY
2025.09.24
【ターナーの人生と代表作】モネと似ている?印象派の先駆け?

はな
-

STUDY
2025.07.15
シャガール『誕生日』:遠距離恋愛を乗り越えた彼女への愛が爆発したロマンチックな作品

はな
-

STUDY
2025.07.09
ゴヤ『1808年5月3日、マドリード』恐ろしさの裏に隠された背景を読み解く

はな
-

STUDY
2025.07.07
描かれたのは5人の娼婦?ピカソの『アヴィニョンの娘たち』を簡単に解説!

はな
-

STUDY
2025.06.05
「大天使ミカエル」の役割と描かれ方を解説!【キリスト教美術史】

はな

はな
イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。
イタリア・ローマ在住美術ライター。2024年にローマ第二大学で美術史の修士を取得し、2026年からは2つめの修士・文化遺産法学に挑戦。専攻は中世キリスト教美術。イタリアの前はスペインに住んでいました。趣味は旅行で、訪れた国は45カ国以上。世界中の行く先々で美術館や宗教建築を巡っています。
はなさんの記事一覧はこちら